
敬愛するツワモノ変態カメラマン諸氏達がマイクロフォーサーズやAPS-Cフォーマットのカメラで叩き出す数々の素晴らしい画を拝見して心を揺すぶられ、PENTAX K-5以来となるAPS-Cシステムをサブではない過酷ロケ用小型システムとして検討し、6月末の発売日にX-T10を導入しました。
約3ヶ月間そこそこ使い込んだので、備忘録としてインプレッションを纏めてみました。
※ あくまでも思い入れを含んだ個人的主観によるものであります。
長所
- 発売キャンペーンでもらったハンドグリップを付けても、とにかく小さくて軽い。合わせてレンズ群も小さく軽いので機動性は抜群。
- 富士フィルムのX-Seriesすべてに共通する事であるが素の色が素晴らしい。自分の感覚では適正露出(普通の人に比べて-2/3段だけど)& 適正WBの場合には殆んどいじる必要性を感じない。
- Auto White Balanceがとても優秀。大きなハズレのないD4SのAWBと比べても遜色ないと感じる。
- フィルムシュミレーションが秀逸。
- 特にクラシッククロームはデジタルの調整ではなかなか出せないコダクロームを忠実に再現している(と感じる )。
- PROVIA、VELVIAに関してはフィルムのPROVIA100、VELVIA50の方がよりこってりしていた印象があるが、慣れてしまうと十分再現しているように感じる(S3Proの方がより近かった気がする)。但しASTIAはフィルムのそれとは全く別物(最初「?」と思った)。
- 自分にとっては初めてのバリアングルモニターを使うのがとても楽しい(匍匐撮影しなくて済む)。
- X-T10とXF18-55mmのチビッ子コンビでギラギラ太陽入れても迷うことなくピントが来る。
- キットレンズのXF18-55mmが予想に反して素晴らしく優秀。解放で使う頻度の少ない自分は特にそう感じる。願わくばF2.8スタートでなくてもいいから16mmスタートにして欲しかった。
- 短期間で構築されたXFレンズラインナップが素晴らしい(現在所有しているのは、14mm, 27mm, 35mm, 60mm, 18-55mm, 55-200mmの6本)。
- D4Sで使えなくなったSDメモリーカードが流用できた。
- レンズ口径が小さいので各種フィルターが安価
短所
- 小さくて軽いことにより慣性モーメントが働かずぶれやすい。
- ホールド感はX-Pro1の方が圧倒的に良いと感じる(自分の感覚的に適正サイズはX-Pro1)。
- ダイナミックレンジが狭い(あくまでもJPEGの話であり、RAWにはデータが記録されています)
- デフォルトパラメータだと粘りも何もなくいともあっさりとアンダー側が潰れる(Nikonがアンダー側に強いので余計にそう感じる)。
⇒ (追記) 「シャドウトーン」をマイナス側に設定することによって簡単に回避できます。 - ダイナミックレンジ200%に設定するにはISO400まで上げる必要がある。もちろんJPEGでの話であり、RAWではカメラ本体で何を設定しても無視される。
- 明るい画が主体の人であれば気にならないレベルかも。
- デフォルトパラメータだと粘りも何もなくいともあっさりとアンダー側が潰れる(Nikonがアンダー側に強いので余計にそう感じる)。
- ストロボ関連仕様が貧弱(失敗させないためという話を聞いたことがありますが、ここまでしなくても・・・)
- シンクロスピード1/180は遅すぎ。Godoxをオフカメラで使う場合にはシンクロ限界値が実測で1/160(1/180でシャッター幕が出る)。
- 純正ストロボですらハイスピードシンクロができない(今時信じられない仕様に唖然とした)。
- 連射モードにするとストロボシンクロ信号が出ない(最初は嘘だと思った)。
- マニュアル露出操作時のダイヤル操作が中途半端。
- 軍幹部のSSダイヤルにないSS数値を選択する場合には、軍幹部のSSダイヤル操作に加えて前ダイヤル操作が必要。
- ISO感度はメニューから後ダイヤルで設定。
- 結局アナログダイヤル操作で完結するのは絞りだけ。
- 純正の現像ソフトでもカメラ内現像と同じ結果にならない → 現像結果に拘るとそのカメラを手放せない。
- 電源ボタンが軽い。バックの中で干渉して知らない間にONになっていてバッテリーが消耗していたことがあった。露出補正ダイヤルはその機種のターゲットユーザ層に合わせて固さを変えているらしいが、電源スイッチは違うっしょ。
- XF60mmは写りはいいのだがちょっと逆光が入るとAFが迷いまくる。
気に入っているシステムなのに思うがままに書き綴ると短所の方が多いって・・・。
実際にフルマニュアルで使う機種として使いやすいかと言われると、明らかに "No~!" です。
絞り優先かつ自然光中心で使うのならEVFも優秀なので使いやすいのではと思います。
じゃあ何でそれでも気に入っているのかと言われると、「叩き出される色」この一点に尽きます。カメラの機種に関わらずRAW現像で自分の好みの色彩に仕上げられるテクニックを持っているなら別ですが(ちばっち師匠のように)、自分には現像ソフトをどうこねくりまわしてもこの色は出せないので。
X-T1の十字キーが初期ロットから事実上仕様変更されているということで、ホールド感の向上を目的にX-Pro1とX-T10をニコイチにしての移行に先日グラリときましたが、より小さい事が武器になる場面は必ずあるのでX-T10の良い点を最大限生かした使い方をしていきたいと思っています。
ただ、X-Pro2が出たら間違いなくニコイチにしてX-Pro2にいきます(^^ゞ
次回はその気に入っている「フジの色」のRAW現像プロセスの違いによるアウトプットの差異に関して検証してみます。
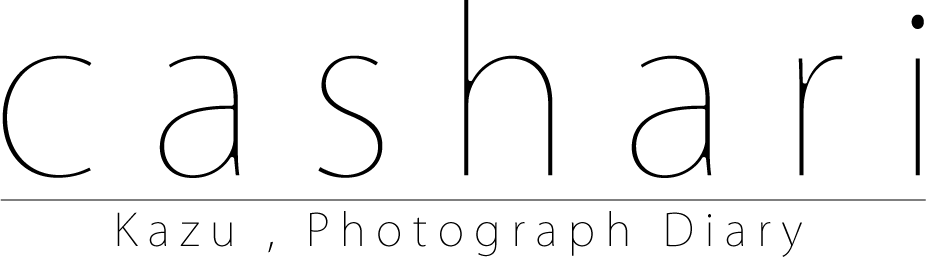
プロ機との比較ではかわいそうな気もしますがぁ
僕の場合にはぁ古い 1DX より進化した E-M1 の方がトータルで勝ってしまった感ありましたねぇ
それと過酷な美マージュ撮影会ぃ雨や海と山岳にとで撮影に集中出来るシステムが優位と思いますぅ
しかしながらぁ個撮で作品撮りとなると叩き出す描写が全てですかぁどこかに不満が有ってはならないですねぇ
次世代の E-M1 がカラーディプスやダイナミックレンジが広がればもう不満も有りませんがぁ
現状はフル機 D800E は手放せません
Kazuさんも2台をシーン毎に使い分けが出来てぃぃですねぇ
>ちばっちさん、
ありがとうございます。
確かにD4Sと比べちゃいけないですし、用途をわきまえて使い分けようと思ってます。
古いと言っても現役フラッグシップのプロ機をE-M1が体感で上回るとは!!
確かに美マ以外が主体であれば軽量システムを組む必要はなかったのかもと思いますね、靴も美マ用に3足増えたし(^^ゞ
一時期はD4S必要ないんじゃないかとも思いましたが、やはり懐の深さの違いは大きく、ご指摘の通りおのずと屋内はD4S中心、過酷系はX-T10中心、スナップはX-Pro1となっていきそうです。
やはりちばっちさんもD800Eは手放せませんよね。お互い贅沢病にかかっちゃってますね(^^ゞ
こんばんは~
dark-sideでカッコ良く黒光して物撮りされたD4SとX-T10が鎮座してますね!
過酷ロケ比率の高い昨今、着々とFuji機でシステムアップされていく様子を指を咥えて眺めてます。
このX-T10を使ったことはありませんが、Kazuさんや他のユーザーの方々のレビューを拝見すると『JPEG撮って出し』で使えるカメラかと。
Fujiの開発の方向性は『カメラ内現像』で完結のような気がします。
ただSYNC速度が1/180とは焚き焚きカメラマンにはキツイですね~
続きをお待ちします。
>華さん、
ありがとうございます。
D4Sと並べるつもりはなかったのですが、より小ささが強調されると思って超簡易ライティングでDARKSIDEで誤魔化しました(^^ゞ
確かに露出もWBも構図も一発で決められる力があって、後処理はごみ取り程度で済ませられるカメラマンなら、JPEG撮って出しのメーカーの設計思想に忠実にいい画が出せるんでしょうけど、なかなかそううまくは行ってくれません~!!
ご指摘の通り「カメラ内現像完結」と「ストロボ使うな」の方針に関しては何とかして欲しいです~(>_<)